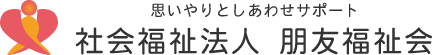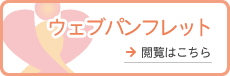行事紹介
令和5年度 年間行事(予定)
4月 ちぎり絵作り | 5月 藤の花作り | 6月 絵はがき作り |
7月 朝顔フレーム作り | 8月 ストロー花火作り | 9月 敬老会 |
10月 ランプシェード作り | 11月 紅葉ちぎり絵作り | 12月 ビンゴ大会 |
1月 しめ縄作り | 2月 プラ板作り | 3月 フォトフレーム作り |
令和4年度 年間行事
4月 しだれ桜作り | 5月 しおり作り | 6月 和綴じ作り |
7月 風鈴作り | 8月 うちわ作り | 9月 敬老会 |
10月 万華鏡作り | 11月 小物入れ作り | 12月 ビンゴ大会 |
1月 タオルうさぎ作り | 2月 ちぎり絵作り | 3月 コットンボールライト作り |
令和3年度 年間行事
4月 ちぎり絵(春) | 5月 藤の花作り | 6月 絵はがき作り |
7月 朝顔フレーム作り | 8月 ストロー花火作り | 9月 敬老会 |
10月 ランプシェード作り | 11月 紅葉ちぎり絵 | 12月 ビンゴ大会 |
1月 しめ縄作り | 2月 ブラ板作り | 3月 フォトフレーム作り |